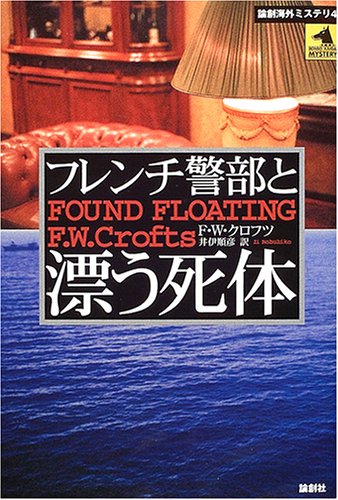Found Floating
1937年発表 フレンチ警部16 井伊順彦訳 論創海外ミステリ
前作『船から消えた男』
次作『シグニット号の死』
ネタバレなし感想
本作のテーマは王道中の王道、富豪の一家に巻き起こる親族間の争いです。人生の晩年に差し掛かり気力体力ともに衰えを感じている経営者、才能はあるが不真面目な甥と望まれない後継者、一家を切り盛りするため悪戦苦闘する女性と何かをひた隠しにする姪。彼らが一堂に会する場所で騒動が起こらないはずはありません。
設定は王道ですが、その後起こる事件はまったく予想だにしない展開をむかえます。ここはクロフツの意外に器用なところというか、遊び心がある部分です。そして、この遊びの部分の中に、しっかりと本編の伏線と手がかりが含まれているのは言うまでもありません。
クロフツもののもう一つの楽しみ、作者のマニアっぷりがわかる詳細過ぎる描写も健在です。本作が発表された前後数年は、たぶん船ブームだったようで『ヴォスパー号の喪失(遭難)』『船から消えた男』『シグニット号の死』と立て続けに船が登場するミステリを世に送り出しています。本書でも、中盤の一番大事であろう二、三章がほとんど船の描写で埋まっているのは、なんともクロフツらしいと言えるでしょう。
また、地中海クルーズの魅力を伝える中東の叙景描写も精緻で、旅行好きのフレンチ警部の捜査そこのけの熱中ぶりがユーモラスに描かれています。
フレンチ警部の捜査、と言いましたが、実際に登場するのは中盤以降。フレンチ警部の出番が来るまでは、事件が起きた地元の警察が担当していて、いつものように地元警察では解決できない難事件がまわりまわってスコットランドヤードに到達してくるというわけです。
ここも「クロフツ、巧いなあ」と思う部分なのですが、持ち込まれ型の事件を捜査するフレンチ警部のよくある導入っていうのは、事件について「ちょっと知ってるけど、詳しくは知らない」レベルのぼんやりとしたもの。ここで地元警察がやってきて、一から丁寧に説明を始め、その後フレンチ警部は自問自答のようにおさらいをしながら、疑問点・不可解な点を一つずつリストアップしてゆきます。この過程が読者に対するフェアプレイ&カインドネスの表れなんですよねえ。一度関係者の目線で物語をなぞってから、改めて探偵の視点で事件を検討させてくれる、この徹底した親切心こそクロフツ作品の長所と言っても良いかもしれません。
じゃあ、2回も丁寧に事件を検討できるんだから、謎解きだって軽めでしょ?とお思いかもしれませんが、本作の難易度は高めです。というのも、ある重要な手がかりが完全に(しかも意図的に)隠されているからなのですが、決してフェアプレイを遵守していない!と非難される類のものではなく、手がかりが隠された必然性、そしてその他の物的・状況証拠はこれでもかと揃っています(というかフレンチ警部が勝手に揃えます)。
他にも細かい点で推しポイントが多いんですよ。例えば、ホームズものを彷彿とさせる味わい深い解決編では、古典ミステリの醍醐味をとくと味わえる形になっていますし、ロマンスも“古き良きイギリスのラブコメ”って感じがして実に良き。短いながらも温かみのあるエピローグは読者に寄り添った証だし、フレンチ警部ファン向けにはフレンチ夫人の久々の登場というサプライズも待っています。
トリックだって、切り取って眺めてみるとめちゃくちゃ手が込んでて、しかも新奇ですからね。添え物が渋めなだけで、名トリックのポテンシャルは秘めてますからね。
元々地味なフレンチ警部シリーズの中で、際立った名作というわけではありませんが、見どころのとても多い作品なのは間違いありません。
以下超ネタバレ
《謎探偵の推理過程》
本作の楽しみを全て奪う記述があります。未読の方は、必ず本書を読んでからお読みください。
舞台設定はよくあるパターンなので、このまま行けば邪魔者のマントもしくはウィリアムが消され、ジムに容疑がかかる展開になるだろう。
慣習通りの推理にはなるが、もちろんジムが犯人ではないだろう。遺産目当てのジェリコーとかだと面白そうだが。
屋敷での中毒事件は誰にも犯行の機会があるので一端推理からは外しておく。船で起こったマント殺害のトリックを解き明かすほうが先決。
気になったのは、マントの死体の傷。足首に巻き付いたロープ痕と切断傷。閃いたのは、船から死体が遺棄され、それが船のスクリューに接触して切り傷がついた。これは良い線いっている気がする。
問題は船からマントが下船した記録があること。入れ替わりトリックぐらいしか思いつかないが、なんとなく前提条件としてはマント下船は確実に見える。
となると、犯行に人数をかけることができるダグデール夫妻が疑わしいが、下船したマントを殺して改めて船内から遺棄するメリットがあまり無いように思える。地中海のど真ん中で沈んでくれれば見つからずに済むのは確実だが。
最終盤、ウィリアムの過去/身辺調査をするに至って、ようやく犯人が見えてくるがこれではほぼ負けと言っていい。
犯人
ウィリアム・キャリントン(動機:過去に犯した過ちをネタに被害者から脅迫されていた。トリック:親族ゆえに似ていることを利用した変装トリック。)
遺体に結び付けていたロープが船のスクリューで切られなかったら間違いなく完全犯罪になっていただろう。それだけ完成度が高い事件だった。
一件目の中毒事件であっさり死んでいれば、ウィリアムとは違う別の人間が誤認逮捕されていたかもしれない、と考えると、これで良かったのかもしれない。
ウィリアムとマントの関係が周到に隠されていて、仄めかしすら無いのが一見アンフェアにも思えるが、よくよく考えてみるとそうでもない。
たとえ彼らの関係が手がかりとして提示されていたとしても、マントの招集とウィリアムの療養/転地/引退が、ウィリアム自身の意思で行われているように書かれているし、船でウィリアムが体調を崩したのもジェリコー医師によって保証されているので、真っ直ぐウィリアムを疑う状況に無かった。また、ジェリコー医師が客船での旅行を勧めたように見えているのも巧い(頁136)。スクリューの不運を除けば、ウィリアムは上手く時機を掴んで犯行を実行したことになる。ウィリアムが泳ぎが得意な伏線もちゃんとあった(頁5・274)
あえて気になるところを挙げるとするなら、ウィリアムじゃなくてもジムでもジェリコーでもルーク(・ダグデール)でも誰でもマントに変装できた可能性を排除していないこと。よく見たらウィリアムがマントに「似ている」それだけで、ウィリアムが犯人だと論理的に証明できているわけではない。まあ、この中で上陸せず船に残っていた人物はウィリアムただ一人なので、①船内から遺体を遺棄しなければならなかった(遺体への工作の時間が必要)、②マントに化けて一度上陸し、泳いで船に戻ってくる必要があった(濡れたまま再上陸は不可能?)という理由から、ウィリアム犯人説はかなり強固になる。
2004年になってようやく初訳、ということですが、これは論創社天晴!ってゆうか本書って、論創社の“論創海外ミステリ”の創刊に際し発表されたんですね(発表順は4番目)。今では250作を超える長寿シリーズの最初期を支えた一冊ということでしょう。面白くないわけがないですよ。
では!