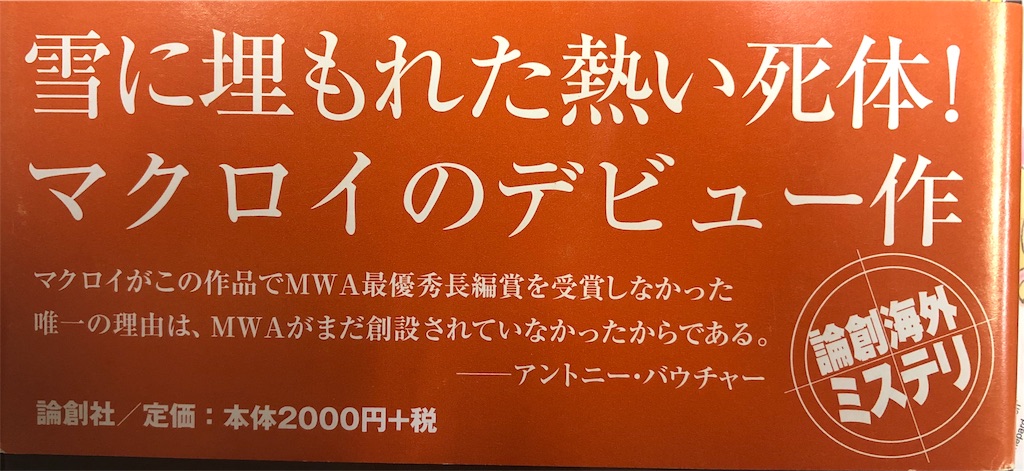発表年:1918年
作者:M.D.ポースト
シリーズ:アブナー伯父
訳者:菊池光
今年は短編集を読む機会が少なく、結局たった7作品しか読めなかったのですが、その中でも断トツにお勧めしたい短編集が本書です。まずは初ポーストということで作者紹介から。
M.D.ポーストという男
メルヴィル・デイヴィスン・ポーストは1869年牛や馬の飼育で生計を立てている一家の長男として、アメリカ・ウエストバージニア州に生まれます。そんな環境から子どものころから牛や馬と触れ合う活発な少年でしたが、大学では法律について学を深め卒業後は弁護士として腕を振るいながら、夢であった作家にも果敢に挑戦してゆきます。
個人事務所の開設、結婚、子どもの誕生など順風満帆に見えた矢先、生後18か月で愛息子が他界。ポースト夫妻は深い悲しみを癒すため、仕事も辞めヨーロッパ旅行に赴きます。この時の経験が活きたのか、ポーストはイギリスの大衆雑誌にも連載を開始するようになり、1907年悪徳弁護士ランドルフ・メイスンもので作家としての地位を確固たるものにするのでした。
1914年に実母が亡くなって以降、拠点を故郷に移し、アブナー伯父の短編集を出版。その人気はますます高まります。しかしながら、ポーストの晩年は最愛の妻と父の死も重なり孤独なものだったようです。愛馬〈マーゴ〉を乗り回したり、隣人を招いて会食をしたりと、その孤独を紛らわす中、なんとその愛馬から落馬。その時の怪我がもとで1930年61歳の生涯の幕を閉じました。
本書「アブナーもの」も面白いんですが、それ以上に気になったのが、もう一つの主要シリーズ、史上初の悪徳弁護士ランドルフ・メイスンもの。法の抜け道を利用して犯罪者の無罪を勝ち取る、というのが大筋なようで、めちゃくちゃ面白そうなのですが、『クイーンの定員』に選ばれている作品しか邦訳では読めないのは残念すぎます。こちらも邦訳化が待ち望まれるシリーズかもしれません。
探偵役アブナー伯父について
一言で表現するなら、史上最も戦闘力の高い探偵、それがアブナー伯父です。推理小説の勃興から100年以上経ち、銃をバンバンぶっ放す探偵も数多く登場してきましたが、神の威光を感じさせる厳格で絶対的な力を持った探偵はアブナー伯父ただ一人です。
以下、本書第一編『天の使い』の一文です。
彼は、戦う教会の一員で、彼の神は、軍神である。
(一瞬、関羽かなんかかな?とは思いましたね)
常にポケットには聖書が入っており、気が向いたらいつでも読む、みたいな信心深いエピソードと全くマッチしない激烈な性分に最初は面食らうはずです。
しかし、直接的な暴はほとんどなく、聖書の警句や神への畏怖などの人々の信仰心に火をつけるような巧みな話術にこそ、彼の本質が感じられます。
似たような聖職者探偵ブラウン神父とは一味違い、第一印象からひとかどの人物であることがわかる超個性的な探偵ですが、決して非人間的ではなく、むしろ純粋に悪を憎む正義感の強すぎるおじさん、それがアブナー伯父なのかもしれません。
この「伯父」ですが、本編の語り手がアブナーの甥である9歳のマーティン少年だからで、彼はポーストの少年時代を投影したキャラクターだと言われています。
9歳の男の子の視点ですから、少年らしいユーモラスな筆致も魅力の一つなのですが、同時にアブナー伯父に対する羨望と畏敬の念もひしひしと感じられます。
あと書いておかなければならないのは、本書の舞台が1800年代前半のアメリカ開拓時代だという点。
アブナー譚が初めて世に出たのが1911年ですから、本書は約100年前を舞台に書かれたある意味歴史ミステリであり、さらには作者ポーストの目線で書かれた自伝的推理小説という点も忘れてはいけません。
本書を読んで200年前のアメリカに旅立ち、アブナー伯父とともに開拓時代の熱気溢れる厳しくもエネルギッシュな物語を堪能してください。
各話感想
『天の使い』(1911)
語り手マーティンとアブナー伯父の初登場作品です。
銀行など全くない時代、金の支払いという重要任務に就いた9歳の子どもの視点で物語は進みます。
謎と解決というミステリの根幹部分はアブナー伯父に丸投げ状態ですが、罪を犯す意を決した人間の表情はとても印象的です。
『悪魔の道具』(1917)
短編集にはお馴染みのの盗難事件が題材です。
単純なフーダニットに落ち着くのではなく、盗難品の性質がちゃんとミステリに反映されているので、想像以上にサプライズを感じる一編です。アブナーの推理小説作家としての力量を推し量るにはもってこいの作品です。
『私刑(リンチ)』(1914)
状況証拠に基づいて結論を急ぐ危うさを、「私刑」を通して表現した異色作です。
はっきりと謎が提示されるわけでも、どんでん返しがあるわけでもないのですが、アブナー伯父の果たす役割には捻りが利かされています。
『地の掟』(1914)
摩訶不思議な状況で消失と出現を繰り返す金貨のお話。不可能色溢れる題材と、濃い登場人物たちが印象に残る佳作です。
しっかり手がかりも提示されており、短編としての完成度が高いだけでなく、事件を〈魔女の伝説〉に絡めるなどエンタメ性も十分。
『不可抗力』(1913)
本書の中でも上位の一作です。
“神の御業”としか言いようがない不可抗力による事故で死んだ男が、如何にしてその不幸を身に招いたのか。
解決までのプロセスに明らかな欠落があるのは事実ですが、そこが補完されていれば屈指の名作短編になっていたであろう作品です。オチもアブナー譚を代表するかのような印象的なものになっています。
『ナボテの葡萄園』(1916)
ここにきてシンプルな殺人事件が登場します。仔細を分析してしまうとただの捜査記録以上のものではないかもしれませんが、物的証拠に着目し、法廷という魅力的な舞台の中で大どんでん返しをやってしまう手腕には脱帽です。
オチまで勢いを落とすことなく、スピード感があるのも特徴でしょう。本書を代表する一編であることに違いはありません。
『海賊の宝物』(1914)
いやあ巧い一編です。
遺産相続に絡む招かれざる放蕩息子の帰郷、というよくあるテーマの事件。
もちろん真相はあからさまに目の前にぶら下がっているのですが、解決までの過程に工夫が凝らされています。最後の一言がビシッと決まるのも快感です。
『養女』(1916)
こちらもシンプルな殺人事件。
“養女”を取り巻くドロドロとした雰囲気も良いのですが、やはり決定的証拠を頼みの綱にしたその構成力に目を見張るものがあります。もちろん、時代を考慮しないといけない部分もありますが、本書の中では好きな一編です。
『藁人形』(1917)
本書中ベストを決めるなら間違いなく本作です。
一見どこにでもある強盗殺人のように見える事件ですが、現場の状況には不審な点ばかり。ちゃんと犯人を指し示す決定的な証拠も巧妙に描かれており、フェアプレイの観点でも満点。100年以上の時の経過にも耐えうる名作短編です。
また、アブナー伯父の探偵観にも読み応えがあり、ミステリファンには是非ともお勧めしたい逸品です。
『偶然の恩恵』(19??)
迫力満点の一編が登場します。
サプライズを犠牲にして描かれるのは、アブナー伯父と犯罪者のヒリヒリとした一騎打ち。
話が進むにつれ事件の全容が少しずつ明らかになり、緊張感が高まっていくのが堪りません。何度読んでも楽しめる一作です。
『悪魔の足跡』(1927)
殺人が題材の“馬”ミステリです。
開拓時代のアメリカという背景と、事件が起こる舞台、そして小道具が絶妙にマッチした作品ですが、他の短編に比べると似たり寄ったりの部分が多いのも事実。訓話めいた、という点ではブラウン神父譚に通じるものがあります。
『アベルの血』(1927)
骨太のトリックが用いられている点で、本書の中でも注目すべき一作です。
現場に残された手がかりの一つひとつから的確に犯人を指し示すアブナー伯父が圧巻です。
あのクイーンが「完璧なタイトル」と評したのも頷けるオチのゾクゾクした感じ(宗教画っぽい雰囲気も好き)を是非体験してほしいです。
『闇夜の光』(1927)
「夜であった。」という、なんとも意味ありげな書き出しで始まります。
それ以外特筆すべき点はないのですが、脇役のアダム・バード老(『アベルの血』にも登場)が良い味を出しています。
『〈ヒルハウス〉の謎』(1928)
執筆順にしても最後のアブナー譚が本中編です。
ボリュームに比べるとミステリのエッセンスは物足りませんが、やはり解説でも触れられているとおり登場人物の一人がミソです。本作を読んで第一編『天の使い』を読むとまた味わい深いものがあります。
まとめ
論理的に整った素晴らしい短編集というわけではありませんが、1900年代の前半に発表された作品群ということを考慮すると求められるモノは違ったわけですから、そこらへんはご愛敬。
味わってほしいのは、アブナー伯父の迫力ある語り口と、インパクトのある解決方法の数々です。
ブラウン神父とは違い正式な聖職者ではないからこそ導き出せる解決手法は、法という規範意識がまだまだ徹底されていなかった1800年代のアメリカにもピッタリはまっています。
ぜひ昨今の古典ミステリブーム(?)に乗っかって新訳化を切望する短編集でした。
では!
M.D.ポースト 東京創元社 1978-01-20